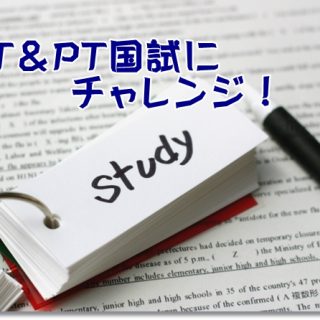みなさん、こんばんは。
崖っぷちの難聴OT林です。
今回は「在宅医療管理」に関するケアマネ一問一答です。
○☓問題に挑戦!
Q1:経管栄養法を導入した場合には、経口から食事を摂取してはならない。
Q2:経管栄養を行なっている高齢者では、便の形状や量が変化するため、その状態により経管栄養剤の変更を検討する。
Q3:胃ろうのバルーンカテーテルが自然抜去しているのを発見した場合は、瘻孔が自然に閉鎖するのを確認した上で、主治医または訪問看護師に連絡する。
Q4:経管栄養の場合には、錠剤の内服薬は投与できないので、点滴治療となる。
Q5:人工透析には大きく分けて血液透析と腹膜透析があり、腹膜透析を行う場合、週3回程度の定期的な通院が必要となる。
Q6:自己腹膜灌流法(CAPD)による人工透析は、在宅での管理が可能であり、血液透析に比べて通院回数が少なくて済む。
Q7:適切な薬物療法などを行えば、がん患者におけるがん性疼痛や呼吸困難などの症状は、在宅においても緩和可能である。
Q8:がんの身体的疼痛は制御が困難で、点滴による麻薬の投与が欠かせない。
Q9:胃ろうによる経管栄養で使用されるすべての経管栄養剤は、医師の処方に基づき医療保険から提供される。
Q10:胃ろう部にスキントラブルのない療養者は、胃ろう部をドレッシング材で被わずに、胃ろう周囲を石鹸で洗うことも浴槽に入ることもできる。
Q11:在宅での医療管理において、尿路感染症を繰り返す介護者については、尿導留置カテーテルをその原因として考慮する。
答えは…(下の方へ)
正解は?
経管栄養法を選択しても、経口摂取ができるときは口から食事をするようにする。
Q2:○
便の形状や量が変化した場合は、経管栄養剤の変更とともに注入速度の変更も検討する。
Q3:✕
閉鎖してしまわないように、すぐにかわりのカテーテルを入れる。
Q4:✕
錠剤の内服薬は投与できる。現在では、懸濁し経管投与する方法を導入している所が多い。
Q5:✕
週3回程度の定期的な通院が必要なのは血液透析である。
Q6:○
CAPDは、月に1、2回通院。
Q7:○
疼痛管理方法や副作用についての教育を行うこと、服薬記録をつけてもらうこと、緊急連絡体制を整備することが重要となる。
Q8:✕
点滴だけでなく、座薬や経口薬による方法も検討する。
Q9:✕
経管栄養剤には、医薬品扱い(保険適用)と食品扱い(全額自己負担)がある。
Q10:○
入浴後、自然乾燥させる。
Q11:○
尿導留置カテーテルの使用は慢性膀胱炎などの尿路感染症のリスクが高くなるため、尿の性状に注意し清潔保持を心がける。
お疲れ様でした!
最後までお読み下さりありがとうございました。
★ブログランキングに参加中!

人気ブログランキング
![]()
にほんブログ村