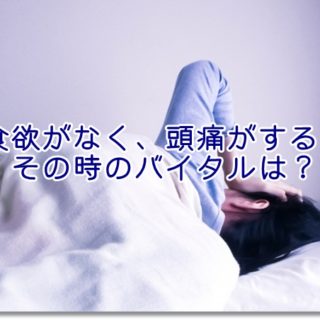拘束がもたらす弊害とは?甘い認識がつい拘束を!
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
昨日の記事「身体拘束に関する小テスト」を書きましたが、全問正解できた人はきっと厚労省のいう身体拘束の定義や判定基準を理解されていると思います。全くできなかった人は、「分かっているつもり」と甘い認識を持っていたのかもしれません。
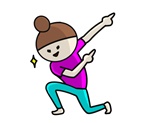
ここでは、身体拘束による3つの弊害と甘い認識が引き起こす拘束についてお伝えします。
スポンサーリンク
身体拘束がもたらす3つの弊害
身体拘束による弊害には、次の3つ。
①身体的弊害
身体機能の低下・圧迫部位の褥瘡の発生・食欲の低下・無理な立ち上がりによる転倒
②精神的弊害
認知の進行・家族への大きな精神的苦痛
③社会的弊害
スタッフ自身の士気の低下・社会的不信・偏見を引き起こす。
拘束が拘束を生む悪循環
身体拘束による悪循環を認識する必要がある。
拘束
↓
体力の衰え
↓
認知の進行
↓
せん妄や転倒
↓
さらに拘束!
最初は一時的として始めた身体拘束が時間の経過とともに常時の拘束となってしまう。
甘い認識がつい拘束を?
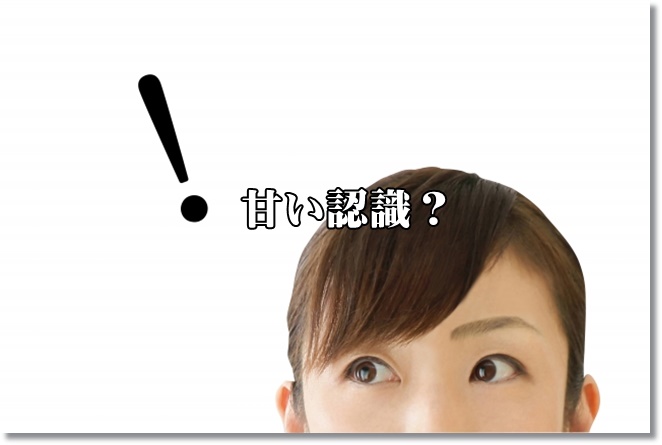
拘束が拘束を生む悪循環の背景には、スタッフの認識によるものが多いと思います。甘い認識がつい拘束を生み出してしまうことがあるでしょう。
認識というのは、以下の通り。
職員の共通認識
・マンパワーが足りないことを理由に安易に身体拘束などをしていないか?
・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束などをしていないか?
・高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで、安易に身体拘束などをしていないか?
・認知性高齢者であるということで、安易に身体拘束などをしていないか?
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体拘束などを必要と判断しているか?本当に他に方法はないか?
これらはついやってしまいそうな認識ですが、そういう安易に拘束しようとするのは施設側の一方的な都合になると思います。
甘い認識が拘束を生み出す
そんなことにならないように気をつけたいものですね。