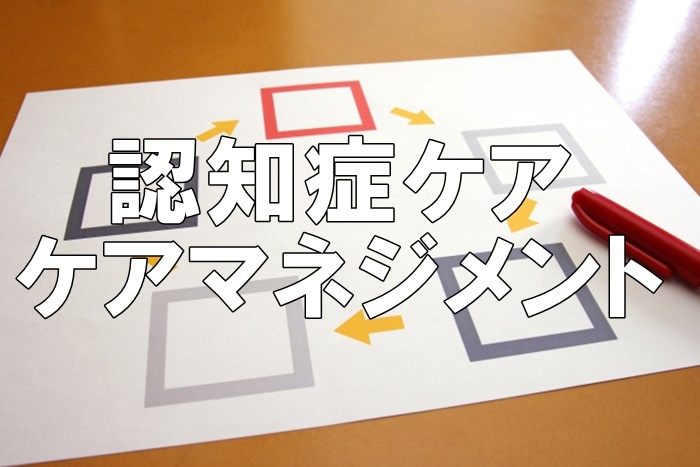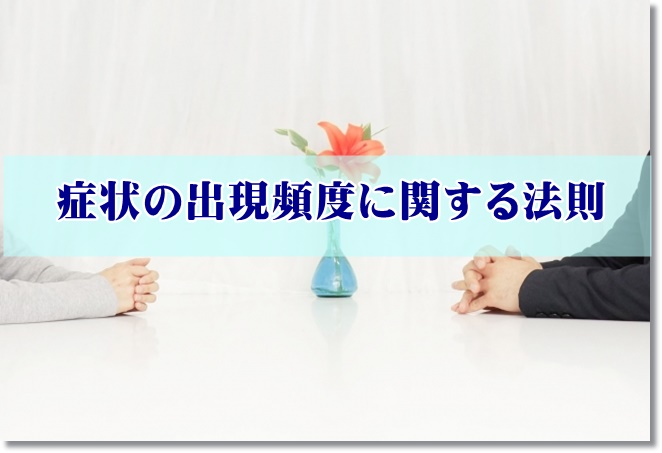
症状の出現頻度のこと。身近な人ほど症状が出やすい?
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
昨日は認知症をよく理解するための9大法則・1原則の①記憶に関する法則をお伝えしました。
今日は法則②についてです。
※認知症ライフパートナーのテキストと過去問を参照。
スポンサーリンク
認知症を理解する法則とは?
では、杉山孝博氏の提唱する、認知症を理解するための9大法則・1原則は以下の通りです。
②症状の出現頻度に関する法則
③自己有利の法則
④まだら症状の法則
⑤感情残像の法則
⑥こだわりの法則
⑦作用・反作用の法則
⑧認知症症状の了解可能性に関する法則
⑨衰弱の進行に関する法則
1原則・・・介護に関する原則
今日は②症状の出現頻度に関する法則についてです。
症状の出現頻度に関する法則
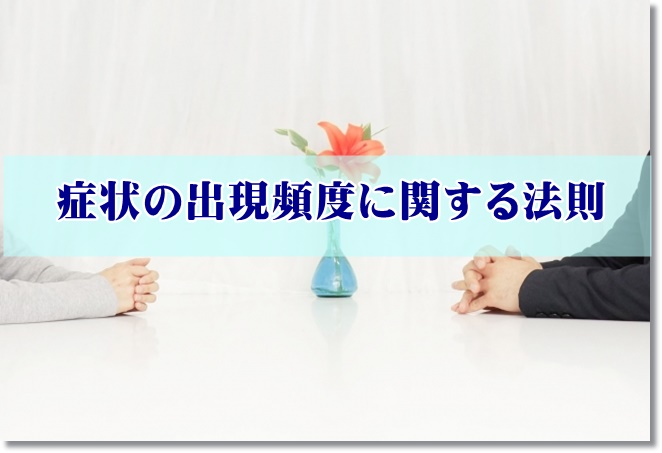
これは、「より身近な人に対して認知症の症状がより強く出る法則」を言います。
毎日介護してくれる最も身近な介護者に対しては認知症の症状が強く出るけど、時々会う人や目上の人には症状が軽く出ることがあります。
この特徴が理解されないと、介護者と周囲の人との間に認知症への理解に深刻なギャップが生じて介護者が孤立するのです。
他人には認知症とは思えないほど、しっかりした対応を取るけど、自分に対してはきっと嫌がらせをしているに違いない!と介護者は悩み混乱することもあるようです。
でも、それは誤った判断なんですね。子供が最も信頼している母親に甘えて困らせるように、介護者を最も信頼しているから認知症の症状を強く出すことがあると判断したほうがよさそうですね。
確かに自分の家族と他人の前とでは対応が違いますよね?他人に対しては体裁を整えたくなるものです。
それが②症状の出現強度に関する法則です。
次回は、9大法則の③自己有利の法則について紹介したいと思います。
最後までお読み下さりありがとうございました。
★ブログランキングに参加中!

人気ブログランキング
![]()
にほんブログ村