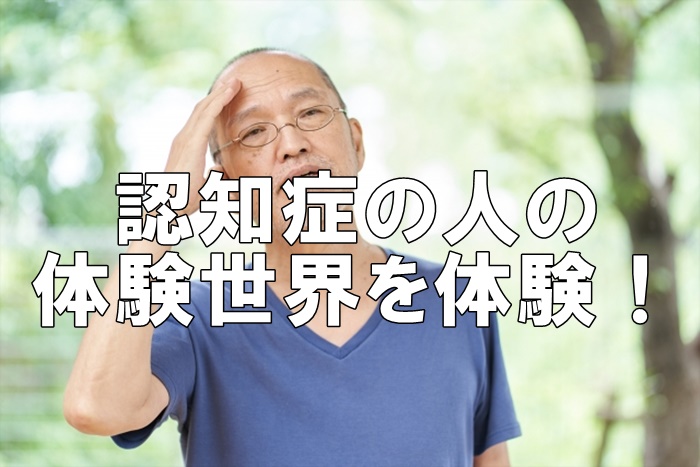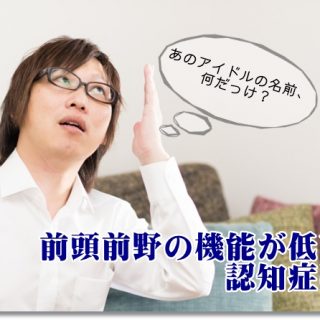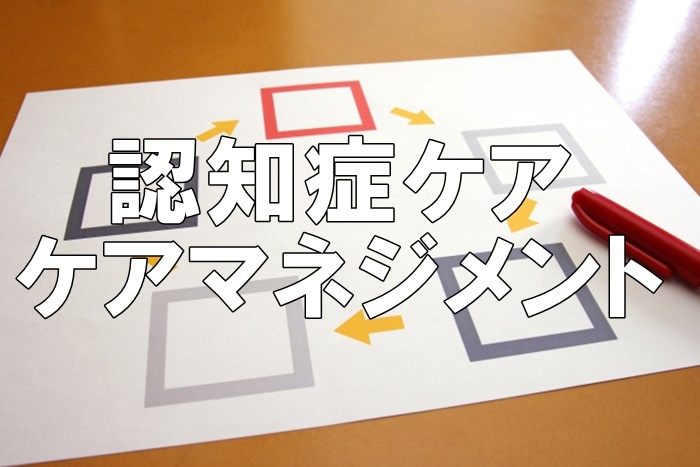
認知症ケアの実践プロセス「ケアマネジメント」
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
昨日、自宅で筋トレやストレッチをしたため、案の定、体中が筋肉痛です。
さて、今日は、認知症ケアを実践する際に重要なプロセスであるケアマネジメントについてお話ししようと思います。
※認知症ケア指導管理士のテキストを参照にしています。
前回、当ブログで家族支援の基本には、①介護環境の調整、②家族への接し方があるとお話しましたが、介護環境を調整するには、ケアマネジメントが有効だと言われています。
認知症ケア指導管理士の役割その③ BPSDと介護環境 みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56) 今日も認知症ケア指導管理士の7つの役割のうち、④BPSDへの対応と⑤介護環境の調整について簡潔に説明 …
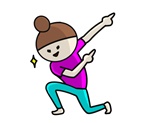
ここでは、認知症ケアの実践プロセス「ケアマネジメント」についてお伝えします。
スポンサーリンク
ケアマネジメント
ケアを受ける人のニーズに応えるため、必要な社会資源を結びつけ、連絡・調整し、利用者の望む生活を実現させるための手法。
アセスメントの目的と視点
アセスメントの目的→利用者の情報収集とニーズの明確化
以下の6つの視点から進めていく。
①生命の安全
目標→健康に過ごすこと。
健康状態が悪化するような点はないか?
認知症の症状であるBPSDに注意する。
②生活の安定
目標→安全に過ごすこと。
日常生活の自立、継続ができているか?
認知症の人の運動機能や危険認知能力の変化に伴い、安全な環境も安全な支援の方法も変化していくことがある。
↓
記憶障害の程度や環境適応能力を十分にアセスメントし、利用者にとっての快適性を考慮する。
③人生の豊かさ
目標→残存能力を十分に活用すること。
その人らしい生活ができているか?
環境設定によって、残存能力が引き出されることもある。
④安心と快適
目標→安心で快適であること。
不安や不快な状態である点はないか?
人間関係や環境、活動状況などに着目する。
⑤残存能力
目標→その人らしさが継続されること。
自分の力が発揮しているか?
今までの生活様式や習慣、生活リズム、なじみの関係など、利用者の思いを大事にアセスメントする。
⑥支援体制
目標→お互いに支えあうこと。
利用者本位で支えられる資源はないか?
認知症の人とその家族が、地域や近隣の人たちとのつながりをもちながら生活しているか?
支援者からの一方的な視点ではなく、介護者と利用者のこれまでの歴史にも着目することが大切。
今日はここまでにしますね。次回は認知症ケアを実践する際のケアマネジメントの進め方について紹介します。
最後までお読み下さりありがとうございました。
★ブログランキングに参加中!