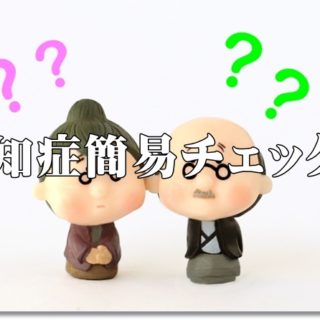認知症ケアコミュニケーションのコツ⑦正しく伝えるために言葉で「話す」
みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)
今日は、認知症ケアにおけるコミュニケーションの最後であるコツ⑦の正しく伝えるために言葉で「話す」をお伝えします。
※公式テキスト認知症ライフパートナーを参照。
スポンサーリンク
認知症ケアにおけるコミュニケーションの7つのコツ
①自分の態勢を「整える」
②治療・援助者が希望を持ち「まなざす」
③希望というまなざしを向けて「共にある」
④対象者の心の開きを「待つ」
⑤対象者の生活機能とその思いを「知る」
1.聴く
2.「観る」、「集める」、「読む」
⑥その思いを言葉に頼ることなく「伝える」
⑦正しく伝えるために言葉で「話す」
※①~⑥をクリックすると該当記事ページに飛びます。
以上の7つが認知症ケアにおけるコミュニケーションのコツです。
今回は、いよいよ最後の⑦の正しく伝えるために言葉で「話す」のことを説明します。
正しく伝えるために言葉で「話す」
⑦の正しく伝えるために言葉で「話す」の基本には、以下の通り5点あります。
1.言葉を物として手渡す
2.訓読みを活かす
3.言葉を活かす作業
4.作業を活かす言葉
5.言葉が活きるタイミング
ここでは、管理人が参考になった1と3,4,5のポイントに触れます。
言葉を物として手渡す

これは言葉の意味が十分に伝わらない対象者に、言葉の意味に頼らず、物を手渡すときのように「言葉」を相手に渡すというものです。
コミュニケーションが苦手な方やケアの初心者に対して、認知症の人とのコミュニケーションのトレーニングとして推奨されている方法なんですね。
以下がその方法です。
1.手渡すことができる距離まで近づき、
2.アイコンタクトを取る。そして、物を手渡し、受け取るために、
3.双方の態勢が整うのを待つ。そして態勢が整えば、
4.相手の受け取り能力(覚醒度、認知能力)に合わせて、
5.手渡す「言葉」の量を考え、
6.手渡す(話す)速さを配慮し、
7.受け取る(聞く)準備が出来たことを確認して、
8.一度に理解できる量(内容)を手渡す(話す)。そして続けて話しかけるときには最初に手渡した物(言葉)を、
9.相手が受け取った(聞いた)ことを確認して、
10.次の物(言葉)を手渡す。
1から10までの流れをイメージしてコミュニケーションを取ります。
アクティビティと言葉

言葉が十分にコミュニケーションの機能を果たさない対象者には、アクティビティを媒体にします。
1.図示したものや写真などを示しながら話す(視覚的イメージ)
2.具体的に見て触ってもらいながら話す(具体的な感覚情報)
3.似通った体験を通して話す(類似体験)
4.実際に行なって見せながら話す(例示体験)
5.実際に行なってもらいながら話す(具体的体験)
6.共に行いながら話す(共有体験)
これらは、実際に身体感覚を通して体験されたことを活かした言葉の使い方をすることです。
アクティビティ・ケアを用いる際には、これらを上手に活かしておくことで、認知症の人とのコミュニケーションが十分に取れるのではないかと思います。
言葉が活きるタイミング
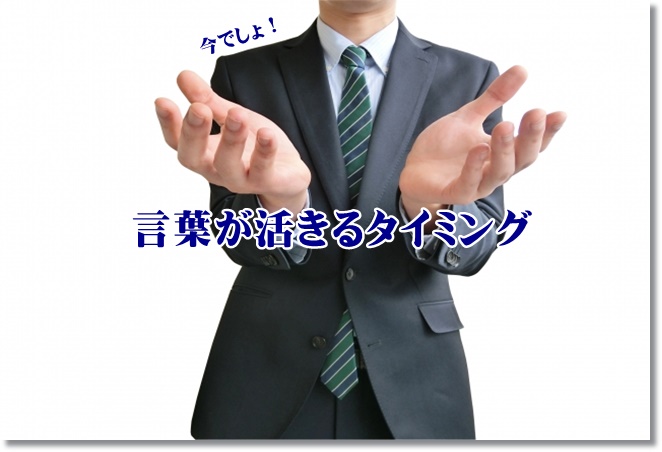
体験したことが意味あるもの、確かなものとして記憶されたり学習されたりするには「言葉」をかけるタイミングがあります。
リハビリ現場でも、対象者によくフィードバックしますよね?
セラピストが「そうです!上手ですよ!」と言葉をかければ、対象者は「そうか、これでいいのか!」といった納得が記憶、学習としてニューロンネットワークを形成し強化することが大切です。
で、言葉が活きるタイミングは、認知症の人の場合は今、ここでのよいタイミングで声を掛けることがポイントです。
もう古いですが、林修先生のキャッチフレーズである「今でしょ!」と同じ認識ですね(?)
さいごに
以上が、認知症ケアにおけるコミュニケーションの7つのコツでした。
どのコツも認知症ケアへのコミュニケーション力を身につけるのに大切な要素ですので、一つずつコツを繰り返し生かせればスキルとして身につくと思います。
ぜひ現場でコミュニケーションの際に活かしてくださいね!
最後までお読み下さりありがとうございました。
★ブログランキングに参加中!

人気ブログランキング
![]()
にほんブログ村